年収300万円でもできる子育て政策
概要
年収300万円でもできる子育て政策
「子どもを育てたい」と思ったとき、それを経済的に諦めずに済む社会へ。
概要
私たち労働党は、年収300万円台でも安心して子育てできる社会を「普通の人の願い」として真正面から受けとめ、具体的な政策群として提案します。
特に若年層・共働き・ひとり親といった不安定な就労条件にある世帯が、保育・教育・医療・住居・就労の全般にわたって過度な負担を抱える現状を変える必要があります。
「自己責任だから仕方ない」ではなく、「制度で支えることはできる」と示すことが、少子化の克服にもつながると私たちは信じています。
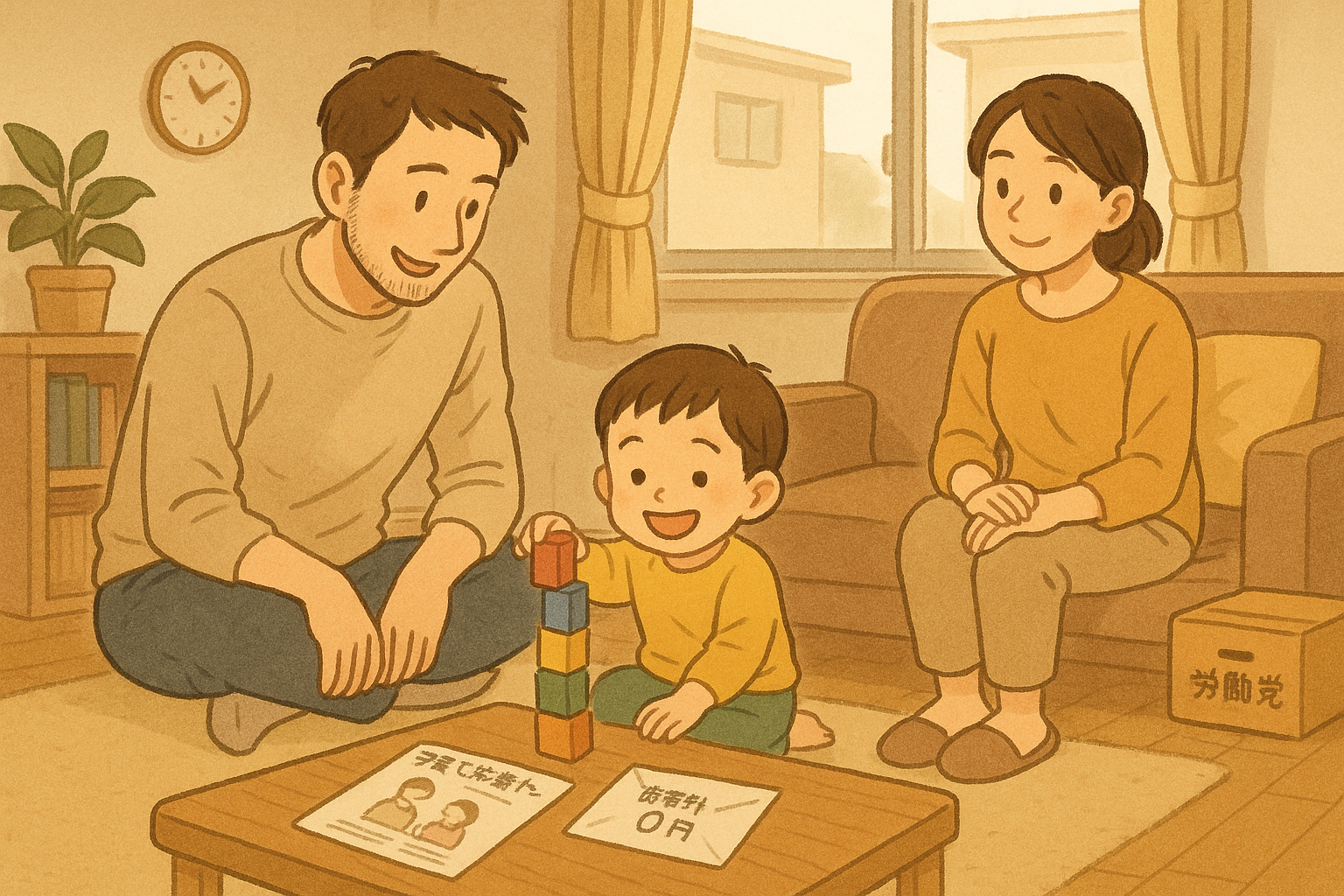
なぜ必要か?
現代の若い世代が子どもを持つことをためらう最大の理由は、経済的な将来不安です。特に、年収300万円台の共働きやひとり親世帯では、「育てたいけれど無理かもしれない」という葛藤が日常的に続いています。 保育料や家賃の高さ、教育・医療の出費、そして仕事との両立困難が積み重なることで、精神的にも経済的にも追い詰められてしまいます。 実際にその中で子育てしている家庭も、「常にギリギリで余裕がない」「頼れる人がいない」「子どもに必要な体験を与えられない」と感じています。
このような状況は、少子化を加速させるだけでなく、子どもたちの将来の機会格差を固定化し、社会全体の活力低下にもつながりかねません。 私たちは、個々の家庭の責任ではなく、制度設計の問題としてこの現実に向き合います。
目指す社会像
私たちが目指すのは、「子どもを持ちたい」と願うすべての人が、経済的な理由でその希望を諦めなくて済む社会です。
年収や家族構成に関係なく、安心して子育てに踏み出せる環境を整えることは、少子化対策のためだけではなく、社会全体の活力を高める投資でもあります。 保育・教育・医療などの基本的なサービスへのアクセスにおいて、家庭の経済状況が壁とならないように支援を再設計します。
地域には、妊娠期から思春期まで一貫して相談や支援を受けられる拠点が整備され、どの家庭も「ひとりじゃない」と感じられるようにします。 特に、困難な環境で育つ子どもたちにも公平なスタートラインを保障することで、分断や格差を次世代に持ち越さない社会を実現します。 国と自治体が柔軟に連携し、制度のすきまを埋める形で、多様な家族のかたちに対応していきます。
年代別モデル家族とその課題・支援
妊娠・出産・乳児期(0〜2歳)
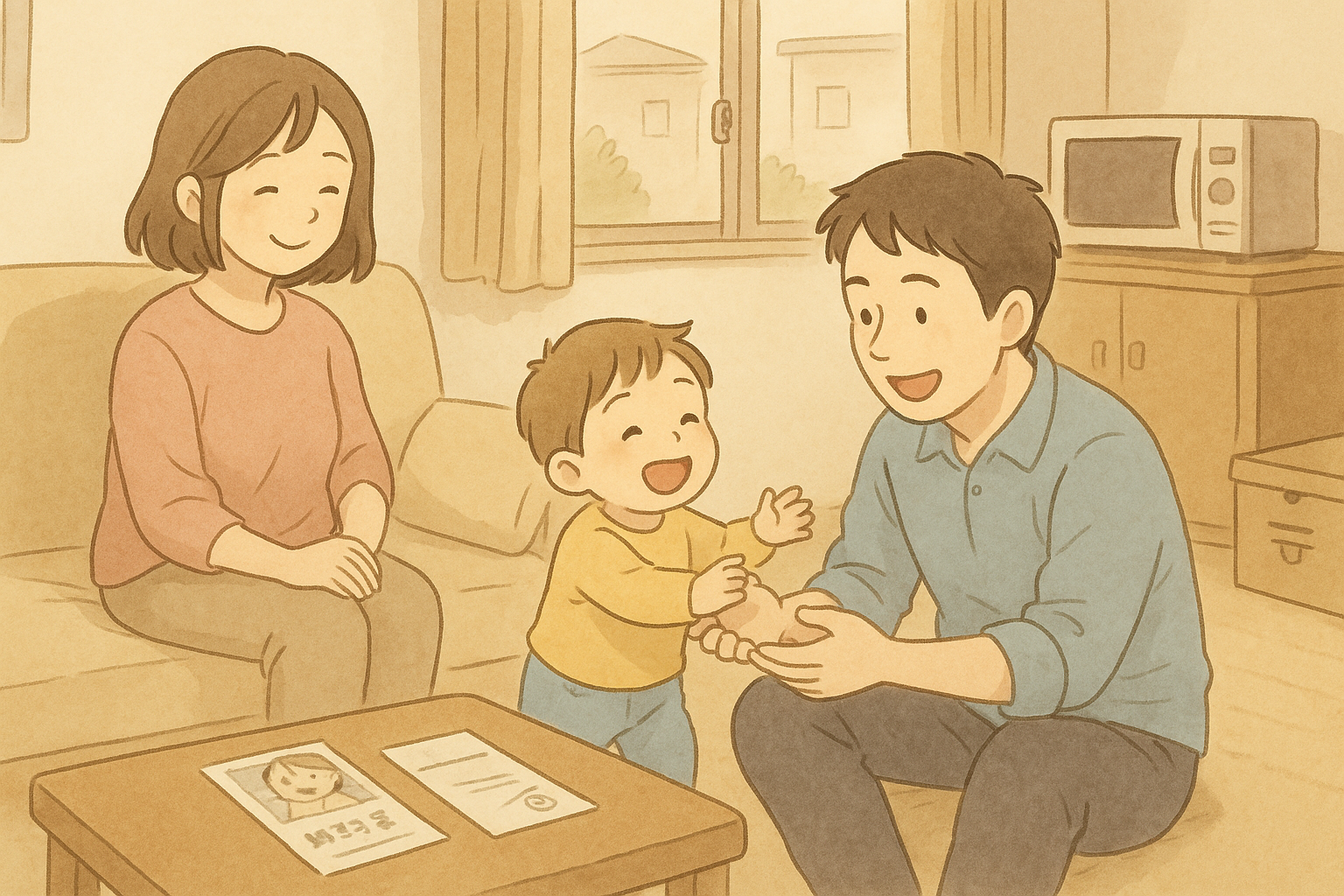
モデル家族
- 夫:27歳、正社員(中小企業・サービス業)、年収約300万円
- 妻:26歳、パート勤務 → 妊娠で休職中、現在収入ゼロ
- 子:0歳(第一子)
- 居住:地方都市圏の築20年アパート(家賃約5.8万円)
設定意図と設定根拠
本モデルは、「できるだけ若いうちに子どもを持ちたい」と考える家庭を想定しています。
国全体としても少子化対策の観点から、初産年齢の低下は重要な目標です。夫を20代後半とした理由は、初産の平均年齢(女性:30.9歳)よりやや早く、かつキャリアも発展途上の層であるため、支援の再現性と政策的意義の両立を図るためです。
年収300万円という水準は、国税庁や求人系統計に基づくと、25〜29歳男性の年収分布における下位15パーセンタイル前後に相当します。
これは「本当に困窮している層」よりも一歩上にある、“就労意欲もあり生活を維持しているが、出産・育児にあたって経済的・心理的な困難を感じやすい層”を対象としています。
労働党の政策では、このような家庭が「なんとかなる」ではなく、「安心して子どもを育てられる」と実感できるよう、出産・育児初期から支える制度設計を重視しています。
※本モデルは、再現性のある支援設計を示すために「下位15パーセンタイル前後」の家庭を想定しています。
より困難な状況(生活保護世帯、年収200万円未満、母子家庭等)にある家庭については、別途、追加的・重点的な支援策(児童扶養手当、現物給付、生活支援型の就労保障など)を段階的に検討・整備していきます。
月収および月の支出シミュレーション(支援なし)
- 想定世帯可処分月収:約20万円
- 想定支出:家賃・食費・光熱費・子ども用品などで月18万円
- 月間黒字:+2万円(ただし突発的出費や将来の備えには脆弱)
| 支出項目 | 金額(円) |
|---|---|
| 家賃 | 58,000 |
| 食費 | 40,000 |
| 光熱費・通信 | 20,000 |
| 子ども用品(オムツ・ミルク等) | 15,000 |
| 医療費・通院等 | 5,000 |
| 交通費・ガソリン等 | 8,000 |
| 日用品・雑費 | 10,000 |
| 娯楽・交際費 | 5,000 |
| 貯金・予備費 | 10,000 |
| 合計支出 | 171,000 |
| 月間収支(余剰) | +29,000 |
※ベビーカー・ベビーベッド・チャイルドシートなどの初期一括支出(7〜15万円程度)は含まれていない。
想定される生活上の困難
初期費用の捻出が困難
出産直後に必要なベビーカー、ベビーベッド、チャイルドシート、抱っこひもなどの初期費用は7〜15万円程度とされ、月々のわずかな黒字では到底カバーできません。
「必要だとわかっていても、全て中古でそろえるしかない」「安全性より安さを優先せざるを得ない」といった声もあります。
精神的な孤立と疲弊
妻は妊娠を機にパート勤務を離職しており、育児をほぼ一人で担っている状況です。近所に頼れる親族もおらず、出産や夜間の授乳、体調の変化に耐える中で誰にも相談できない孤独感を抱えています。
「夫も忙しく、頼りたくても申し訳なくて言い出せない」「泣き声を誰かに聞かれるのが怖い」といった精神的な疲弊も深刻です。
就労復帰・保育園確保への不安
妻は「また働きたい」と考えているものの、保育園の空きがあるか不明な上、自治体ごとの保活(保育所探し)情報もバラバラで、見通しの立たなさが復職意欲にブレーキをかけています。
さらに、夫の勤務先も子育てへの理解が十分とは言えず、突発的な病気や夜間対応時の調整にも不安が残ります。
将来設計の余裕がない
生活自体は回っていても、「2人目は無理」「学資保険も入れていない」「マイホームは夢のまた夢」といった声が現実です。
制度が支えてくれなければ、この生活は“なんとか続ける”ことしかできず、“未来を選ぶ”ことはできません。
支援策
-
産前産後の母子保健強化
助産師訪問、産後ケア、一時預かり支援を自治体経由で公的に整備します。
出産後の孤立や産後うつのリスクを軽減し、「孤育て」を防ぎます。
👉 詳細を見る -
子ども支援センター構想
児童館・乳児院・保健センターなどを統合した、地域一貫型の子育て支援拠点。
出産から就学前まで切れ目のない相談・保育・医療支援を提供します。
👉 詳細を見る -
夜間・一時保育の整備
シフト制・非正規・多様な就労形態に対応する柔軟な保育体制を、地域ごとに再構築します。
👉 詳細を見る -
育児スタート準備給付(仮)
出産直後の家庭に、ベビー用品の購入や育児スタートに必要な現物または5〜10万円程度の給付を支給します。
東京都「赤ちゃんファースト事業」などの先行事例を参考に、全国で再現可能な制度を目指します。
(今後検討・追加予定) -
妊娠期・育休給付前の生活支援
妊娠届の提出から育児休業給付金の支給開始までの「空白の半年間」を補う、月5万円・最大8か月の無利子・無担保貸付制度を創設します。
妊娠初期の経済的な不安を和らげ、安心して産前の生活を整えられる仕組みをつくります。
👉 詳細を見る -
パート・非正規向け育休補完給付(仮)
雇用保険に未加入の就労者に対し、出産・育児期に簡易な現金給付制度を導入。
シフト勤務・短期契約でも「育てる時間」を失わずに済むようにします。
(今後検討・追加予定) -
赤ちゃん用品ライブラリー(地域型)
支援センター等を拠点に、清潔で整備されたベビー用品の寄付・リユース・貸出制度を導入。
経済的負担の軽減だけでなく、地域の支援文化を育みます。
(今後検討・追加予定) -
産後3ヶ月SOS対応制度(仮)
出産後の不安や孤立に即応できる支援体制を、子ども支援センターに常設配置します。
「ごはんを作れない」「数時間でも預かってほしい」「話し相手がいない」といった“限界の手前”の声に応じて、相談・見守り・食事支援・一時預かりなどを柔軟に提供します。
国は制度化・交付金設計・研修整備を担い、自治体が地域に根ざした実施主体となります。
「声を上げたときに、誰かが応えてくれる」——そんな支援を、全国どこでも当たり前にします。 (今後検討・追加予定) -
ハイブリッド母子手帳(紙+デジタル連携)
紙の母子手帳を維持しつつ、QRコードやICチップを用いて、スマートフォンと連携できる機能を追加します。
医療機関での予防接種・健診データをデジタル化し、母子手帳に自動反映させることで、必要な情報を「見落とさず・受け取りやすく・活用しやすく」します。
国がフォーマット・標準API・情報連携ルールを整備し、自治体が導入・交付を担います。
民間事業者と連携した開発・運用を前提とし、医療機関や子ども支援センターと情報がつながることで、妊娠期から就学前までの一貫支援の基盤を構築します。
スマホが苦手な人のためにも、紙ベースの記入機能はすべて保持し、ユニバーサルアクセスを実現します。 (今後検討・追加予定)
支援適用後の再シミュレーション(ビフォー/アフター)
※以下は、「妊娠・出産・乳児期(0〜2歳)」モデル世帯において、政策的支援が適用された場合の家計変化を仮定したシミュレーションです。
支援内容・給付額・物価等は将来的な制度設計によって変動する可能性があるため、あくまでも試算上の想定としてご参照ください。
- 想定世帯可処分月収:約20万円(支援前と同様)
- 育児スタート準備給付:一時給付5万円(初期用品に使用済)→ 月あたり換算:▲8,000円相当
- 赤ちゃん用品ライブラリー活用による消耗品軽減:▲3,000円
- 産後SOS支援による一時保育・家事支援:▲2,000円相当
- 家計への実質的な支援効果:月1.3万円相当の負担軽減
| 支出項目 | 支援前 | 支援後 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 家賃 | 58,000 | 58,000 | ±0 |
| 食費 | 40,000 | 40,000 | ±0 |
| 光熱費・通信 | 20,000 | 20,000 | ±0 |
| 子ども用品(オムツ・ミルク等) | 15,000 | 12,000 | ▲3,000 |
| 医療費・通院等 | 5,000 | 3,000 | ▲2,000 |
| 交通費・ガソリン等 | 8,000 | 8,000 | ±0 |
| 日用品・雑費 | 10,000 | 10,000 | ±0 |
| 娯楽・交際費 | 5,000 | 5,000 | ±0 |
| 貯金・予備費 | 10,000 | 10,000 | ±0 |
| 合計支出 | 171,000 | 158,000 | ▲13,000 |
| 月間収支(余剰) | +29,000 | +42,000 | +13,000 |
この支援によって、突発的支出への備えや次月以降の貯蓄余力が生まれ、「子育てはギリギリ続けられる」から「少し先の計画が立てられる」状態へと近づくことが期待されます。
幼児期(3〜6歳)

モデル家族
- 夫:31歳、配送業(中小企業・契約社員)、年収約250万円
- 妻:30歳、パート勤務(週5日・4時間)、年収約120万円
- 子ども:4歳(保育園・年中)
- 居住:地方都市圏のアパート暮らし(家賃7万円、車1台保有)
- 世帯年収:370万円(可処分所得 約300万円)
設定意図と設定根拠
このモデルは、いわゆる「ワーキングプア型共働き世帯」の一例です。
夫婦ともに働いてはいるものの、正規雇用ではなく、地域や職種の特性上、収入が大きく伸びづらい状況にあります。
それでも生活は何とか成り立っており、「頑張っているのに報われにくい」ことが最大の特徴です。
特に、夫は物流系の契約社員で、収入は安定しているものの昇給はほとんど望めません。妻は育児と両立できる範囲でのパート勤務にとどまっており、扶養内で就労しているため社会保険にも未加入です。
子どもは認可保育園に通っており、保育料は軽減措置があるとはいえ、家計にとっては大きな負担。さらに、教育関連費(絵本、知育玩具、習い事)、車の維持費、食費高騰などが重なり、家計にはほとんど余裕がない状態です。
このモデルは、「制度の隙間に落ちやすいけれど声を上げにくい層」を代表するものとして位置づけています。支援が適切に届けば、安心して子育てを継続できる一方、届かなければ2人目出産や就学以降の進路選択に制限がかかり、「子どもを増やす・伸ばす自由」が経済状況に縛られてしまうリスクが高い層です。
月収および月の支出シミュレーション(支援なし)
- 想定世帯可処分月収:約25万円(年収370万円 × 0.8 ÷ 12)
- 想定支出:家賃・食費・光熱費・保育料・教育費・車の維持費などで月24.5万円
- 月間黒字:+5,000円(ただし教育や医療、突発的支出には対応困難)
| 支出項目 | 金額(円) |
|---|---|
| 家賃 | 70,000 |
| 食費 | 45,000 |
| 光熱費・通信 | 22,000 |
| 保育料 | 25,000 |
| 教育・習い事 | 8,000 |
| 医療費・薬代 | 5,000 |
| 車の維持費(ガソリン・保険) | 18,000 |
| 交通費・日用品・雑費 | 25,000 |
| 貯金・予備費 | 7,000 |
| 合計支出 | 225,000 |
| 月間収支(余剰) | +5,000 |
※小規模な習い事・絵本代・通園用備品など最低限の教育支出を含む。 ※突発的出費(修理・医療・冠婚葬祭)にはほぼ対応不可。
想定される生活上の困難
保育料の負担が固定費を圧迫している
認可保育園に通っていても、世帯年収370万円では保育料が月2〜2.5万円程度発生します(自治体による差あり)。
これは家賃と並ぶ固定費となり、月々の可処分所得に大きな圧力をかけます。
子どもを預けて共働きを維持するために、かえって負担が増えるという矛盾した構造に陥っています。
教育・体験の選択肢が限られる
月1万円未満での教育支出では、絵本・習い事・文化体験のすべてをまかなうことは困難です。
「スイミングは無理」「ピアノは高すぎる」「図鑑も図書館で…」と、教育投資の機会が削られていきます。
その結果、「学びの格差」がこの段階からすでに始まってしまうことになります。
就労と育児の両立が時間的に困難
保育園の送迎・就労・家事・育児をすべて夫婦で分担しても、1日が詰まりすぎています。
時短勤務の妻も、限られた時間の中で仕事と育児をこなす中で、「昇給できない」「安定しない」キャリア形成への不安を抱えています。
夫側も労働時間が長く、実質的に「ワンオペ」になってしまうケースも少なくありません。
「2人目は無理」の固定化
子どもが1人でもカツカツで、2人目を望んでも生活設計が立てられない状態です。
教育費・居住スペース・送迎負担・時間的余裕など、すべての項目が限界ぎりぎりで、
「現実を考えると無理だと諦める」家庭が多くなります。
これは少子化の背景にある“構造的な諦め”の典型例といえます。
支援策
-
保育・教育費の段階的無償化
保育料・副食費・幼児教育の費用について、年収に応じた段階的無償化を進めます。
私立園・認可外を含めた負担軽減も対象に含め、地域間格差を緩和します。
👉 詳細を見る -
家賃補助・住宅支援制度
子育て世帯を対象に、家賃補助または公営住宅の優先入居枠を設け、家計固定費を軽減します。
👉 詳細を見る -
ベーシック・オキュペーション(柔軟な就労保障)
地域で「必要だけど賃金にならない仕事」を自治体が発注し、短時間・断続的な仕事でも公的収入が得られるようにします。
子育て中のパート層でも、保育時間に合わせて就労と社会参加が可能に。
👉 詳細を見る -
子ども支援センター構想
保活のサポートや一時預かり・病児対応・相談窓口などを一元化し、「手探りの育児」から脱却します。
👉 詳細を見る -
学びの機会パス制度(仮)
習い事・知育玩具・地域イベント等の費用に使える「育ちの体験補助券」を支給。
「学びは贅沢品ではない」という価値観を制度で保障します。
(今後検討・追加予定) -
幼児向け送迎支援モデル事業(仮)
保育園の送迎に困難がある家庭に対し、子ども支援センター経由で「地域送迎補助員」や交通費助成を実施。
家庭の労働可能性を下支えします。
(今後検討・追加予定) -
子ども見守り活動者総合補償制度(仮)
保育補助・送迎支援・学びの体験同行など、子どもを預かる・同行する支援者向けに、事故時の損害賠償リスクを軽減する自賠責型の公的保険制度を整備します。
国が制度設計と共済的仕組みを構築し、子ども支援センターに登録された活動者に自動付帯。
これにより、支援者の参入ハードルを下げ、保護者側にも安心感を提供します。
(今後検討・追加予定)
支援適用後の再シミュレーション(ビフォー/アフター)
※以下は、「幼児期(3〜6歳)」モデル世帯において、政策的支援が適用された場合の家計変化を仮定したシミュレーションです。
制度内容や給付額は今後の設計により変動する可能性があり、あくまで想定上の試算です。
- 想定世帯可処分月収:約25万円(支援前と同様)
- 保育料段階的無償化(年収階層に応じて):▲25,000円
- 学びの機会パスによる習い事・教材補助:▲5,000円
- 家賃補助(低所得子育て世帯対象):▲10,000円
- 実質的な支援効果:月4万円相当の負担軽減
| 支出項目 | 支援前 | 支援後 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 家賃 | 70,000 | 60,000 | ▲10,000 |
| 食費 | 45,000 | 45,000 | ±0 |
| 光熱費・通信 | 22,000 | 22,000 | ±0 |
| 保育料 | 25,000 | 0 | ▲25,000 |
| 教育・習い事 | 8,000 | 3,000 | ▲5,000 |
| 医療費・薬代 | 5,000 | 5,000 | ±0 |
| 車の維持費 | 18,000 | 18,000 | ±0 |
| 交通費・雑費 | 25,000 | 25,000 | ±0 |
| 貯金・予備費 | 7,000 | 7,000 | ±0 |
| 合計支出 | 225,000 | 185,000 | ▲40,000 |
| 月間収支(余剰) | +5,000 | +45,000 | +40,000 |
これらの支援によって、毎月の「教育・住居・保育」の不安が和らぎ、「2人目を考える余裕」や「貯蓄の開始」が現実的な選択肢として浮上します。
小学生期(7〜12歳)

モデル家族
- 母:39歳、シフト制勤務(サービス業/パート+短期派遣などの掛け持ち)、年収約280万円
- 子:小学4年生(9歳)
- 居住:都市近郊の賃貸マンション(2DK・家賃6.8万円)
- ひとり親世帯、親族からの継続的支援はなし
- 車なし/通勤・送迎は電車と自転車
- 世帯年収:280万円(可処分所得 約220万円)
設定意図と設定根拠
このモデルは、全国に数多く存在する「就労しているひとり親世帯(特に母子家庭)」を代表しています。
2022年時点で母子家庭の平均年収は約251万円(厚労省「全国ひとり親世帯等調査」)とされており、このモデルの280万円はその中でも比較的安定した部類に属しますが、それでも生活には余裕がありません。
この家庭は、母親が育児と就労を同時にこなすために、複数の非正規職を組み合わせる「パッチワーク型の働き方」をしており、収入は流動的かつ不安定です。
一方、子どもは小学校中学年に進み、放課後の時間をどう過ごすか・どのような支援が受けられるかが家庭の安定に直結する段階にあります。
学童保育は夕方には終了し、延長も限界があり、かといって1人で留守番させるには不安が残ります。
病気やけがなどで急に預け先がなくなった場合、母親は仕事を休まざるを得ず、結果として収入や雇用継続にも影響を及ぼします。
また、周囲の家庭が中学受験や塾通いを始める中、金銭的・時間的な事情でそうした選択肢が持てず、教育格差を実感しやすいフェーズでもあります。
このモデルは、「日々を何とか回しながら、将来に対して無力感を抱えやすい層」の代表です。労働党の支援策は、こうした家庭が**「自分の子にもちゃんと未来がある」と信じられる社会**をつくることを目的としています。
月収および月の支出シミュレーション(支援なし)
- 想定世帯可処分月収:約18.5万円(年収280万円 × 0.8 ÷ 12)
- 想定支出:家賃・食費・光熱費・学童・学用品・通勤費などで月18.3万円
- 月間黒字:+2,000円(病児対応や教育費が増えれば即赤字化)
| 支出項目 | 金額(円) |
|---|---|
| 家賃 | 68,000 |
| 食費 | 35,000 |
| 光熱費・通信 | 18,000 |
| 学童利用料 | 6,000 |
| 学用品・教材費 | 5,000 |
| 医療費・子どもの通院等 | 5,000 |
| 通勤交通費 | 10,000 |
| 日用品・雑費 | 10,000 |
| 貯金・予備費 | 6,000 |
| 合計支出 | 163,000 |
| 月間収支(余剰) | +2,000 |
※塾・習い事は行っていない前提。 ※病児保育利用や短期休職が発生すれば、即赤字化・収入減となるリスクあり。
想定される生活上の困難
放課後の「空白時間」に対応できない
学童保育は一般的に18時頃までで終了し、それ以降の預け先は確保が困難です。
勤務がシフト制である母は、夕方以降の勤務にも対応せざるを得ず、子どもが1人で過ごす時間が長くなることに強い不安を抱えています。
延長保育のある学童もあるが、定員が限られており、自治体間の格差も大きいのが現状です。
教育格差を実感しやすくなる時期
周囲の家庭が中学受験や塾通いを始める中、月1万円を超えるような教育費は現実的ではありません。
学用品や図工・自由研究などの学校内での準備物にも負担感があり、子どもが「自分だけ違う」と感じてしまう場面も増えてきます。
親としても「してあげたいのにできない」という無力感が強くなっていきます。
病児対応で収入が削られる
子どもが体調を崩すたびに仕事を休まざるを得ず、シフトを飛ばすことで収入が減るという悪循環が発生しています。
病児保育がない・または空きがない自治体では、実質的に「家庭しかない」という状態であり、働きたいのに働けない状態を固定化しています。
将来への希望が持てない
生活はなんとか維持できていても、「このまま10年後、どうなっているのか」という見通しが立たない状況です。
子どもが成長するにつれてお金も時間も必要になるのに、それに備える余裕がなく、希望より不安が先に立ってしまいます。
「何もしてあげられなかったらどうしよう」と思いながら、目の前の生活に追われている――それが日常です。
支援策
-
子ども支援センター構想
放課後の居場所、学習支援、病児対応、生活相談などを一体提供。
ひとり親世帯や長時間勤務家庭の不安を一箇所で受け止めます。
👉 詳細を見る -
子ども支援センター・拡充型(仮)
既存の子ども支援センターに、以下の機能を段階的に追加整備します:- 子ども食堂の常設化(夕食提供)
- 夕方19時以降も開所(宿題+見守り+軽食)
- 簡易宿泊室(緊急時に宿泊できるユニット)
自治体とNPO・民間団体の連携体制を前提に、国は設備補助・運営費支援を行います。
(今後検討・追加予定)
-
民間学習支援(無料塾)への公的後方支援
NPO・ボランティア団体が運営する無料塾に対して、教室費・教材費の補助、登録講師への賠償保険加入などを通じて、持続的な活動を国が支えます。
自治体と連携し、学校や支援センターからの紹介も可能に。
(今後検討・追加予定) -
子ども給付つき奨学金(小中対象・仮)
経済困難層を対象に、小学生・中学生のうちから月3,000〜5,000円程度の**「教育目的の給付つき奨学金」**を支給。
学用品・習い事・将来の学費積立に使用でき、進学希望の継続を後押しします。
※将来的には高校生への返還不要型奨学金への接続も想定
(今後検討・追加予定) -
病児保育アクセス保障制度(仮)
病児保育の利用料を公費で軽減/送迎や連携病院ネットワークを拡充。
「休まなければならない親」の負担を制度で引き受けます。
(今後検討・追加予定) -
再就労サポート&柔軟シフト推進策(ひとり親向け)
地域企業と連携し、ひとり親向けに柔軟な就労マッチングや定時帰宅優遇の協定制度を整備。
子育てと生活の両立を支えます。
(今後検討・追加予定)
支援適用後の再シミュレーション(ビフォー/アフター)
※以下は、「小学生期(7〜12歳)」モデル世帯において、政策的支援が適用された場合の家計変化を仮定したシミュレーションです。
支援内容や制度設計により変動する可能性があるため、あくまで試算上の想定としてご参照ください。
- 想定世帯可処分月収:約18.5万円(支援前と同様)
- 子ども支援センター拡充型:夕食・放課後居場所・簡易宿泊の無償化 → 食費・学童・雑費の軽減:▲1.5万円
- 無料塾支援:学習塾費負担不要:▲5,000円
- 給付つき奨学金(月額3,000円):+3,000円
- 病児保育アクセス保障制度による欠勤減少分:▲5,000円相当(仮定)
- 実質支援効果:約月2.8万円相当の負担軽減
| 支出項目 | 支援前 | 支援後 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 家賃 | 68,000 | 68,000 | ±0 |
| 食費 | 35,000 | 30,000 | ▲5,000 |
| 光熱費・通信 | 18,000 | 18,000 | ±0 |
| 学童利用料 | 6,000 | 0 | ▲6,000 |
| 学用品・教材費 | 5,000 | 2,000 | ▲3,000 |
| 医療・子どもの通院等 | 5,000 | 5,000 | ±0 |
| 通勤交通費 | 10,000 | 10,000 | ±0 |
| 日用品・雑費 | 10,000 | 10,000 | ±0 |
| 給付つき奨学金 | 0 | ▲3,000(収入扱い) | +3,000 |
| 合計支出 | 163,000 | 135,000 | ▲28,000 |
| 月間収支(余剰) | +2,000 | +30,000 | +28,000 |
これらの支援によって、これまでギリギリで回していた生活に「ゆとり」と「学びの選択肢」が生まれます。
進学準備・習い事・備えの貯金など、“普通の子ども時代”を保障する土台が整います。
中高生期(13〜18歳)
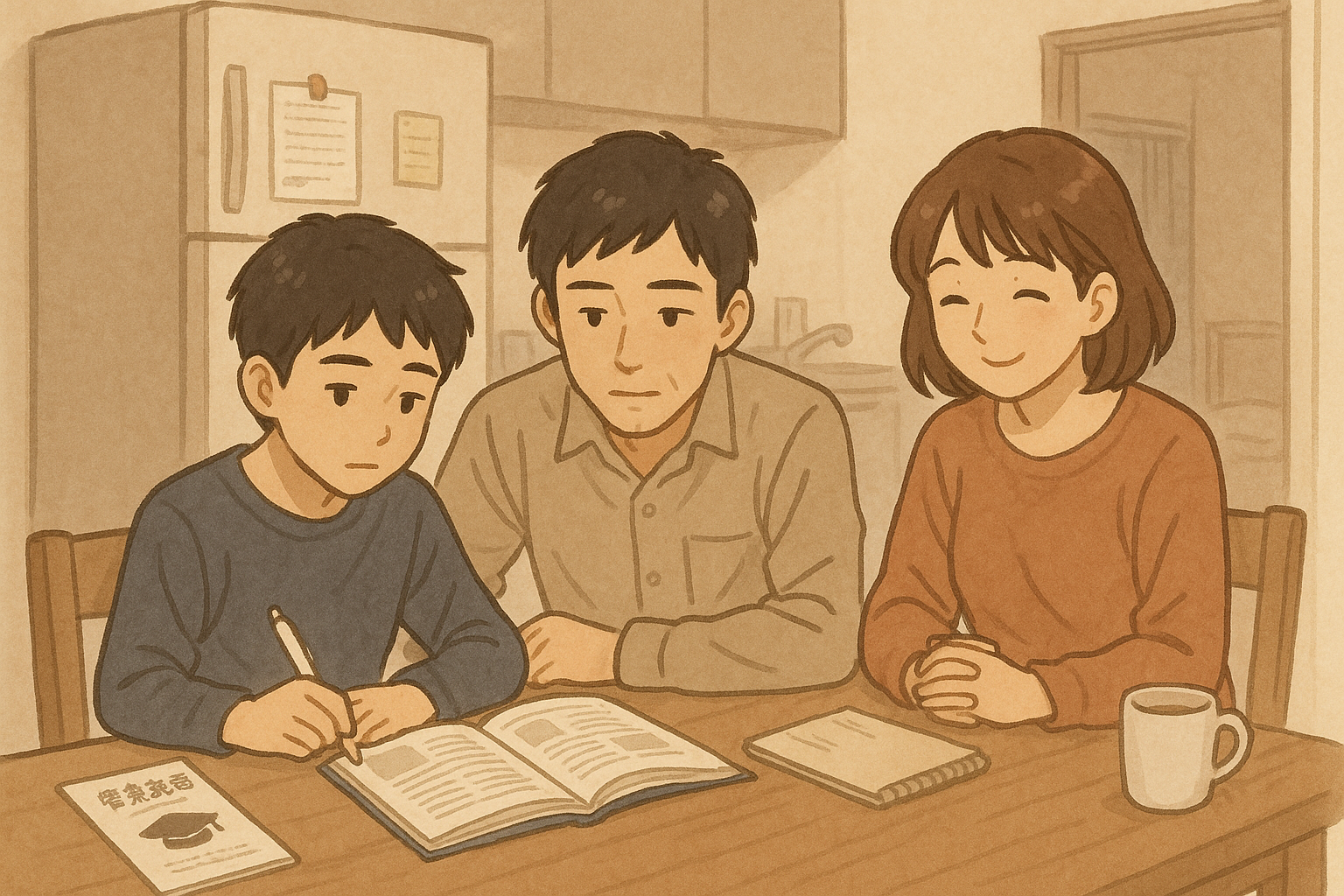
モデル家族
- 父:48歳、短期契約(倉庫業務)、年収約170万円
- 母:45歳、派遣社員(事務職)、年収約150万円
- 子ども:15歳(中学3年生)
- 居住:都市近郊の団地、公営住宅(家賃2.5万円)
- 世帯年収:320万円(可処分所得 約260万円)
設定意図と設定根拠
このモデルは、非正規雇用に依存する中年層の共働き家庭を想定しています。子どもが中学3年生を迎え、「高校進学」「将来の職業選択」「進学塾や模試の費用」といったプレッシャーが一気に高まる時期にあります。
両親ともにフルタイムで働いていますが、いずれも不安定な雇用形態であり、賞与や昇給はほとんど期待できません。長年同じような生活を続けてきたものの、貯金はほとんどなく、教育費の増大に直面した今、経済的にも心理的にも限界に近い状況です。
このモデルの家庭では、「塾に行かせられない」「模試を受けさせられない」「推薦の準備がよくわからない」といった、**“進学以前の不安”**に苛まれています。さらに、親自身が高学歴でない場合、進路指導や情報収集に対して自信を持てず、子どもとのコミュニケーションがすれ違う原因にもなりがちです。
また、思春期の子どもにとっては、家庭での会話が減り、孤立感や焦燥感が強まる時期でもあります。「学校には相談しにくい」「親は忙しそう」「でも進路のことを考えないといけない」――そんなプレッシャーに晒されながらも、誰にも本音を言えずにいる子どもたちの姿を、私たちは見逃してはなりません。
この層への支援は、「貧困の再生産」を断ち切る上で極めて重要です。たった数万円の給付や、たった一人のキャリア相談員との出会いが、子どもの未来を変える分岐点になりうるからです。
月収および月の支出シミュレーション(支援なし)
- 想定世帯可処分月収:約21.6万円(年収320万円 × 0.8 ÷ 12)
- 想定支出:家賃・食費・光熱費・教育費・交通費などで月21.5万円
- 月間黒字:+1,000円(実質的に貯蓄・備えはほぼ不可)
| 支出項目 | 金額(円) |
|---|---|
| 家賃(公営住宅) | 25,000 |
| 食費 | 48,000 |
| 光熱費・通信 | 20,000 |
| 教育費(学校・模試・教材等) | 25,000 |
| 医療・衛生費 | 5,000 |
| 通勤・通学交通費 | 10,000 |
| 雑費・日用品 | 12,000 |
| 娯楽・交際費 | 5,000 |
| 貯金・予備費 | 5,000 |
| 合計支出 | 215,000 |
| 月間収支(余剰) | +1,000 |
※塾代・家庭教師・進学説明会費用などは原則未計上(捻出困難) ※模試・入試関連費用が発生する月は赤字に転落する恐れあり
想定される生活上の困難
進学に向けた準備ができない
中学3年生という人生の分岐点に差し掛かっているにもかかわらず、模試・参考書・受験費用などの最低限の出費ですら負担感が大きく、準備が十分にできません。
「お金のことを考えると、選べる進路が限られる」と子ども自身が感じ始めており、家庭の経済状況が進路選択に影を落としています。
塾・学習支援を受けられない
同級生の多くが塾や通信教育を受ける中、この家庭では月1〜2万円の追加出費すら難しく、塾通いは断念せざるを得ません。
学校の授業だけで受験に臨む不安が大きく、子どもは「自分だけ取り残されるのでは」と感じてしまっています。
子どもがメンタル面で孤立しやすい
両親ともに働いているが不規則な勤務のため、家庭内での会話は最小限。
思春期の葛藤や受験への不安を誰にも打ち明けられないまま抱え込む子どもが増えています。
また、保護者自身が進学経験に乏しいため、キャリア支援や相談の入り口すら見えにくい状態です。
親の不安と無力感が積み重なる
「がんばって働いても生活が苦しい」「勉強させたいけど余裕がない」といった思いが積み重なり、親自身もストレスを抱えがちです。
結果として、子どもの支援に手が回らず、親子関係の断絶やすれ違いが生まれることもあります。
誰も悪くないはずなのに、少しずつ「何もできなかった」という後悔が蓄積していきます。
🛠 支援策
🛠 中高生期(13〜18歳)|支援策一覧
-
子ども支援センター構想(中高生対応)
地域センターに中高生専門スタッフ(学習・進路・メンタル)を常駐。
👉 詳細を見る -
子どもの貧困家庭支援制度
教材費・模試費・制服・食事など、進学準備のコストを現物・現金で柔軟に支援。
👉 詳細を見る -
地域キャリア教育と伴走型支援
職業体験・企業訪問・ロールモデルとの面談を通じて、進路の視野を拡張。
👉 詳細を見る -
進路と学習の個別伴走支援(仮)
中高生に「地域キャリアコーディネーター」が1対1で進路相談・模試フォローを行います。
(今後検討・追加予定) -
中高生向け給付型奨学金(月5,000〜1万円)
模試・受験料・教材・交通費などに使える現金給付を行い、進学継続を後押しします。
(今後検討・追加予定) -
学習支援付き自習室/地域無料塾支援
学校外で安心して学べる居場所を整備。教材費補助や賠償保険付きで、地域と連携して運営。
(今後検討・追加予定) -
メンタルケア・進路不安ホットライン(仮)
24時間・匿名対応のチャット相談を整備。進路・家庭・学校の悩みを受け止めます。
(今後検討・追加予定) -
進路・就職ミニEXPO(中学高校連携型)
親が来られなくても進路の情報にアクセスできる合同説明会を開催。
(今後検討・追加予定)
支援適用後の再シミュレーション(ビフォー/アフター)
※以下は、「中高生期(13〜18歳)」モデル世帯において、政策的支援が適用された場合の家計変化を仮定したシミュレーションです。
支援内容や制度設計により変動する可能性があるため、あくまで想定に基づいた試算です。
- 想定世帯可処分月収:約21.6万円(支援前と同様)
- 教材・模試・受験料の給付型奨学金(月7,000円):▲7,000円
- 地域無料塾・学習自習室の利用:塾費削減 ▲5,000円
- 食費補助(子どもの軽食・弁当支援):▲3,000円
- 子どもの貧困支援制度による通学・衣類等支援:▲5,000円
- 実質支援効果:月2万円相当の負担軽減
| 支出項目 | 支援前 | 支援後 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 家賃(公営) | 25,000 | 25,000 | ±0 |
| 食費 | 48,000 | 45,000 | ▲3,000 |
| 光熱費・通信 | 20,000 | 20,000 | ±0 |
| 教育費(教材・模試・受験等) | 25,000 | 13,000 | ▲12,000 |
| 医療・衛生費 | 5,000 | 5,000 | ±0 |
| 交通費 | 10,000 | 10,000 | ±0 |
| 雑費・日用品 | 12,000 | 12,000 | ±0 |
| 貯金・予備費 | 5,000 | 5,000 | ±0 |
| 合計支出 | 215,000 | 195,000 | ▲20,000 |
| 月間収支(余剰) | +1,000 | +21,000 | +20,000 |
支援により、教育費の不安が軽減され、子どもが塾や模試を諦めずに進学を目指せるようになります。
家庭全体にも月2万円のゆとりが生まれ、「貯められない家庭」が「少しずつ積み立てる家庭」に変わっていきます。
個別政策リスト
| 政策名 | 概要 | 状態 |
|---|---|---|
| 保育・教育費の段階的無償化 | 保育料・副食費・幼児教育費の軽減。年収に応じて段階的に無償化。 | 👉 詳細を見る |
| 家賃補助・住宅支援 | 子育て世帯への家賃補助、公営住宅の優先入居等。 | 👉 詳細を見る |
| 子ども支援センター構想 | 出産〜高校までを支える地域一貫型支援拠点。 | 👉 詳細を見る |
| 産前産後の母子保健強化 | 助産師訪問、産後ケア、一時保育支援の公的整備。 | 👉 詳細を見る |
| 柔軟な働き方の公的保障(ベーシック・オキュペーション) | 短時間就労・地域業務に公的収入を保障。 | 👉 詳細を見る |
| 中高生支援(学習・進路・メンタル) | 学習・進路・メンタル支援を一体で支援。 | 👉 詳細を見る |
| 子どもの貧困家庭支援制度 | 教育費・生活用品・食支援などを柔軟に支給。 | 👉 詳細を見る |
| 国と自治体の子育て政策連携強化 | 交付金・基準・人材などを通じて地域格差のない支援体制を構築。 | 👉 詳細 |
| 妊娠期・育休給付前の生活支援 | 妊娠届の提出から育児休業給付金の支給開始までの「空白の半年間」を補う、月5万円・最大8か月の無利子・無担保貸付制度 | 👉 詳細を見る |
| 育児スタート準備給付 | ベビー用品購入等に5〜10万円給付(例:東京都赤ちゃんファースト参考)。 | (検討・作成予定) |
| パート・非正規向け育休補完給付 | 雇用保険未加入者にも育児休業相当の給付を整備。 | (検討・作成予定) |
| 赤ちゃん用品ライブラリー | 清潔なリユースベビー用品を地域で貸出・寄付。 | (検討・作成予定) |
| 産後3ヶ月SOS対応制度 | 子ども支援センターに即応型支援チームを常設。 | (検討・作成予定) |
| ハイブリッド母子手帳 | 紙とデジタルを連携。QR・ICチップ搭載。 | (検討・作成予定) |
| 学びの機会パス制度 | 習い事・体験費等に使える教育補助券を支給。 | (検討・作成予定) |
| 幼児向け送迎支援 | 保育園送迎支援者への交通費補助・マッチング。 | (検討・作成予定) |
| 子ども見守り活動者補償制度 | 保育補助者向けの自賠責型公的保険制度。 | (検討・作成予定) |
| 子ども支援センター・拡充型 | 夕食・簡易宿泊付きの放課後常設型支援施設。 | (検討・作成予定) |
| 無料塾・学習支援への公的後方支援 | NPO等の学習支援団体へ教材費・保険を補助。 | (検討・作成予定) |
| 子ども給付つき奨学金(小中向け) | 小中学生への月3,000円前後の給付型奨学金。 | (検討・作成予定) |
| 給付型奨学金(中高生向け) | 月5,000〜1万円の進学・受験費用支援。 | (検討・作成予定) |
| 自習室・地域無料塾支援 | 公立施設での学習場所・講師支援を制度化。 | (検討・作成予定) |
| メンタルホットライン | LINE等を活用した24時間相談窓口を設置。 | (検討・作成予定) |
| 進路・就職ミニEXPO | 子どもだけで参加可能な合同説明会を常設。 | (検討・作成予定) |
想定される質問(FAQ)
Q. 本当に300万円で子育てできるの?
→ 支出のうち固定的で高額な「保育・住居・教育」の負担を軽減することで、再現性のあるモデルを作ります。
Q. 高所得世帯との公平性は?
→ 所得制限は段階的に設計される一方、普遍的な制度との組み合わせにより社会全体の子育て支援を底上げします。
Q. 自治体で対応力に差が出るのでは?
→ 国主導で制度設計と財源配分を行い、自治体が柔軟に運用できる形を整えます。