ベーシック・オキュペーション
概要
ベーシック・オキュペーション ── 誰もが社会とつながる柔軟な仕事の保障
「働きたいのに、働く場所がない」
「ほんの数時間だけ働けたら生活が変わるのに」
──そんな声に応える新しい制度が、 ベーシック・オキュペーション です。
私たち労働党は、「最低限の生活保障」だけでなく「最低限の仕事の保障」に国家の責任を明記し、
誰もが週数時間でも“社会に役立てる”仕組みを、制度として整備します。
ベーシックインカムとの違い
この構想は、現代社会におけるベーシックインカム議論から大きな着想を得ています。
しかし、私たちは「お金の分配」ではなく「役割の分配」に重きを置きました。
ベーシックインカムは無条件の給付によって最低限の生活を支えることを目的としていますが、
私たちの提案するベーシック・オキュペーションは、 働く意志があるすべての人に“役立つ場所”を届ける 制度です。
お金だけでは得られない「つながり」や「誇り」を、仕事を通じて支える。
それがこの制度の根幹です。
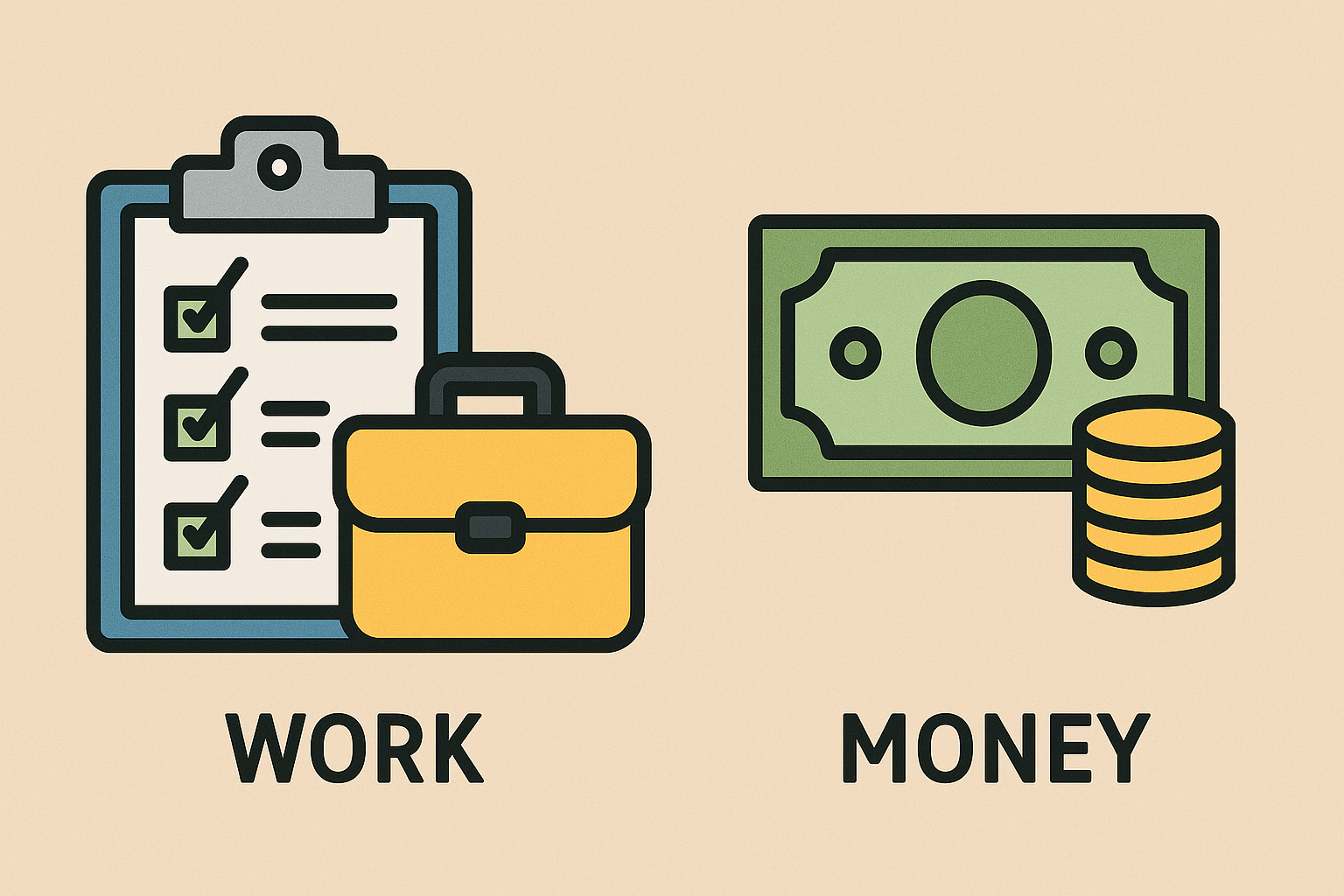
なぜ必要か?
現在の就労支援制度は、対象ごと(高齢者・障害者・若者など)に縦割りとなっており、
窓口や支援内容が分断されています。また、ハローワークなどは職業の紹介機能に留まり、
実際に“仕事そのもの”を用意する仕組みは極めて限定的です。
こうした制度は、それぞれに対象者を想定して設計されているため、
「フルタイム勤務が難しい人」や「長いブランクのある人」 のように、
一つのカテゴリに明確に該当しない人にとっては、
どこに相談すればいいのかすら分からない状況になっています。
また、「働けるほど元気ではないが、完全に支援が必要なわけでもない」人たちは、
制度の枠外に放置されがちです。
特に、介護や育児を担う人、持病や通院がある人、精神的な回復途中の人たちが、
週数時間でも何かできたら──という希望を持っても、それを受け止める制度はほとんど存在しません。
以下に、既存の主な就労支援制度を例示します:
| 状況・属性 | 主な制度 | 主な窓口 | 主な運営主体 |
|---|---|---|---|
| 若者(15〜39歳) | 若者サポートステーション | 地域サポステ | 厚労省・委託NPO |
| 障害のある人 | 就労移行支援・継続支援(A/B型) | 福祉事務所・支援事業所 | 厚労省・市町村 |
| 高齢者(概ね60歳以上) | シルバー人材センター | 地域センター | 地方自治体等 |
| 生活困窮者 | 就労準備支援・生活困窮者自立支援 | 自立支援窓口 | 市町村 |
| 子育て中の親 | マザーズハローワーク | ハローワーク | 厚労省 |
| 離職者全般 | 職業紹介・訓練(ハロトレ) | ハローワーク | 厚労省 |
| 長期ブランク・短時間就労希望 | 対応制度なし | 窓口不明 | 制度未整備 |
| 介護・通院・子育てなどで週数時間だけ働きたい人 | 対応制度なし | 窓口不明 | 制度未整備 |
このように、現行制度は「対象が明確な人」には応じられても、
「条件を満たさない人」や「ちょっとだけ働きたい人」には、そもそも制度が存在しません。
その一方で、日本の地域社会には、“誰かがやらねばならないのに、担い手がいない”仕事が数え切れないほど存在します。
たとえば──
- 子どもの登下校の見守りや付き添い
- ゴミ集積所や公園の清掃、草取り、側溝の掃除
- 高齢者宅の声かけや買い物代行
- 空き家や地域倉庫の管理、防災訓練の手伝い
- 行政手続きの相談同行やデジタル申請のサポート
- デイサービス施設での話し相手や送迎の補助
- 地域イベントやお祭りの設営・片付け
これらの仕事は、地域の民生委員やボランティアが担ってきました。
しかし今や、高齢化・過疎化・担い手不足により、
これまで通り“善意”に頼り続けるのは限界です。
「働きたくても拾われない人」と、「助けてほしくても頼れない社会」。
そのすき間に埋もれた、たくさんの“役に立つ仕事”をつなぎ直すために、
制度の側を変える必要があります。
私たちは、「週に数時間でも誰かの役に立ちたい」
──そんな想いが、社会の一部として正式に尊重される仕組みを提案します。

どんな仕組みか?
私たちは、「最低限の生活」ではなく「最低限の仕事」を保障するという、
新しい就労観を社会に提案します。
ベーシック・オキュペーションは、既存の雇用支援制度や地域公共サービスの枠組みを活かしつつ、
その適用範囲と柔軟性を大きく拡充する制度です。
週数時間から参加できる柔軟な働き方を保障し、従来の制度では拾いきれなかったニーズに応えます。
この制度は、以下の4者の連携により運営されます:
| 担当 | 主な役割 |
|---|---|
| 担い手(市民) | 週数時間から参加できる小さな公共的仕事に従事。属性・年齢・ブランク等を問わず参加可能。 |
| 発注者(地域・事業者) | 既存の自治体・福祉施設・委託業者などに加え、民生委員・自治会・NPOなど地域の担い手も「仕事の発注者」として参加。これにより、これまで制度の外にあった“頼みにくい仕事”も制度内で公的に依頼可能に。 |
| 自治体(基礎自治体) | 地域における仕事と人をマッチング。登録・評価・研修などの管理も担う。既存の公的就労支援を活かしつつ、短時間・柔軟型の就労も支援対象に含める。 |
| 国 | 制度設計、財源保障、インフラ提供(システム・研修・ガイドラインなど)。自治体を技術的・財政的に支援し、全国規模での制度運用を後押しする。 |
この仕組みにより──
- 住民は、「いきなりフルタイム」は難しくても、週1回・数時間の仕事から社会とつながることができます。
- 地域や事業所は、「頼みたいけど頼めなかった仕事」を、制度上の“公的な仕事”として発注できます。
- 自治体は、現行制度の機能を活かしながら、従来は対象外だった就労ニーズにも対応可能になります。
制度の整備は段階的に進められ、以下のような要素が含まれます:
- 地域のケア・教育・環境分野の業務を中心とした柔軟な職務群
- 公的機関・地域団体・民間企業による“発注”機能の制度内化
- 属性にかかわらず広く参加可能な登録制度
- 自治体によるマッチング・評価・研修の仕組み
- 国によるガバメントクラウドなどの標準インフラ整備
私たちは、「ベーシック・オキュペーション」を
福祉でも雇用でも切り分けられなかった仕事の領域に対応するための、
既存制度の拡充としての新たな公共サービスと位置づけています。
実現の道筋と政策群
ベーシック・オキュペーションは、単体の制度として成立するものではありません。
実現には、法制度、情報基盤、運用体制などの複合的な整備が不可欠です。
現在、労働党では以下のようないくつかの関連政策を策定・準備しています。
これらはいずれも制度実現に向けた基盤づくりの一部であり、今後も現場の声や社会状況に応じて、随時追加・検討していく方針です。
-
窓口の一元管理のための法整備
→ 就労支援・福祉・市民活動などの窓口を横断的に整理し、「どこに相談すればいいか」を明確にします。 -
柔軟な就労機会の公的提供のための権限付与
→ 地方自治体が週数時間の仕事を公式に“制度化”できるよう、法的裏付けと財政措置を整えます。 -
制度の垣根を超えた対象者支援
→ 年齢・属性・就労歴を問わず、「やれる人がやれる範囲で」参加できる仕組みを構築します。 -
デジ庁によるガバメントクラウドの開発・提供
→ 発注・登録・マッチング・報酬支払いなどを支える統一クラウドシステムを国が整備・提供します。 -
発注者責任と損害補償の制度化
→ 民生委員・自治会・NPO等が仕事を発注する際、働き手が事故などを起こした場合に備え、損害賠償保険等の加入を義務づける仕組みを整備します(保険料補助も含む)。 -
収入の壁対応のための源泉徴収と年次調整の仕組み
→ 所得が103万円・130万円の“壁”を超えることによる不利益を回避できるよう、自治体が報酬を源泉徴収し、必要に応じて扶養や社会保険への影響を調整する制度を構築します。 -
生活保護受給者向けの段階的報酬控除制度
→ ベーシック・オキュペーションの収入に対して生活保護費の減額を緩やかに行い、収入を得ることが生活保護からの脱却につながる構造を整えます。
また、役割分担としては次のような構図を想定しています:
- 国:制度設計・財源支援・デジタルインフラの提供
- 自治体:地域発注体制の構築・就労者の登録管理・仕事の割当・研修評価など
- 地域担い手:仕事の発掘・発注・実施後のフィードバックなど(報酬付き)
私たちは、この制度が特別な「新制度」ではなく、
既存の公的支援や地域福祉の枠組みに自然に組み込まれ、
「やりたい人」「頼みたい人」「つなぎたい人」が出会える社会インフラとなることを目指しています。
結び──労働党の立場として

「役に立てる場所が、誰にでもある」
その当たり前が、当たり前ではなくなった社会を、私たちは見つめ直したいと思います。
ベーシック・オキュペーションは、働ける人を無理に支援するための制度ではありません。
また、福祉制度に代わる“低コストな労働”を提供するものでもありません。
この制度は、「誰かの役に立ちたい」という人間としての根源的な気持ちを、正当に受け止めるための仕組みです。
労働党はこの制度を、「働くこと」を希望の営みに変えるための一歩と位置づけています。
それは、党の価値観──
- 制度の説明責任と合意形成
- 現実に誠実であること
- 社会をともに支える「共助」の実践
──とも、深く結びついています。
また、私たちが掲げる未来像「黄金の2050年」──
誰もが安心して暮らし、挑戦し、未来に希望を持てる社会を実現するために、
この制度はきわめて基礎的で、実質的な一歩になると確信しています。
「ほんの少しだけ、社会とつながっていたい」
その気持ちが、制度によって尊重される社会へ。
労働党は、そうした社会の実現を、本気で目指します。