支える制度から、納得できる制度へ
概要
高齢者福祉は「支えられること」が当然とされてきました。しかし今、現役世代の限界が近づき、制度そのものの持続が揺らいでいます。
労働党は、高齢者補助を段階的に 半減 し、そのうち1/4を子ども・若者への投資 に、1/4を現役世代の負担軽減に 振り向けます。
同時に、高齢者自身の「誇りある役割」を支える制度へと転換します。
背景と問題意識
日本の社会保障制度は、高齢化の加速とともに拡大し、今や国家予算の約3割が高齢者関連支出に充てられています。 かつては現役世代が高齢者1人を5人で支える構造でしたが、いまや1.7人で1人を支えるまでに縮小しています。
この構造のままでは、働く世代は将来への希望を持てず、結婚・出産・地域活動など、人生のあらゆる選択にブレーキがかかります。 一方で、高齢者全体が困窮しているわけではありません。資産を持つ層と、生活に不安を抱える層との格差が急速に広がっています。
にもかかわらず、補助は「年齢」で一律に支給される──この制度に、もはや現実との接続点は見出せません。
なぜ高齢者福祉は今、見直されるべきなのか?
高齢者福祉制度の見直しは、感情論ではなく、制度の物理的な限界に直面しているからです。
支える人が減り、支えられる人が増えている
かつて日本では、5人の現役世代が1人の高齢者を支える構造が成立していました。 しかし今やこの比率は2.0人で1人を支える水準にまで低下し、2070年には1.3人で1人を支えるという試算もあります1。
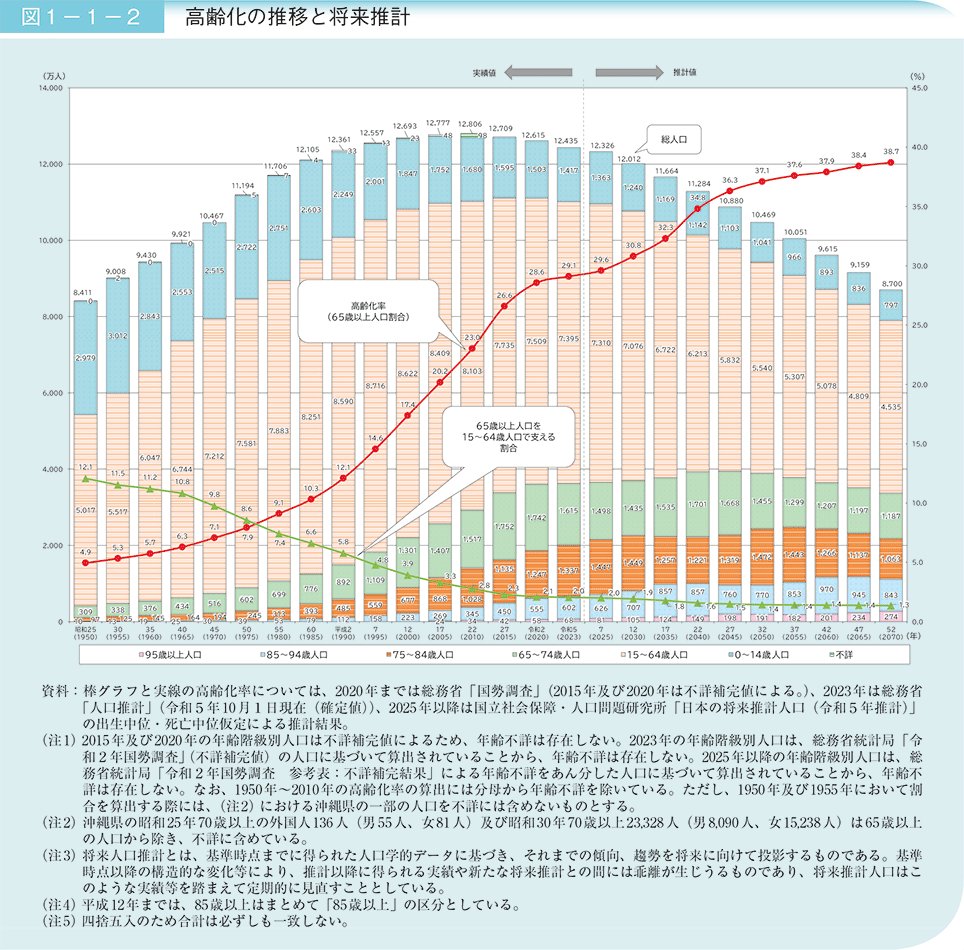
高齢者の数が増える一方で、支え手である現役世代が減っている―― この単純な構造変化が、制度そのものの持続可能性を根底から揺るがしているのです。
社会保障費と社会保険料が膨らみ続けている
国家予算における社会保障関係費は、令和6年度(2024年度)で約37.7兆円と、一般会計(112.6兆円)の約3割以上を占めています2。 その大部分は、年金・医療・介護など高齢者向け支出が占めています。
一方、制度を支えているのは現役世代が納める社会保険料です。 たとえば、会社員(40歳以上)は健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料などを合わせて、年収の2〜2.5割近くを天引きされています。
さらに、社会保障給付費全体(2021年度)は約138兆円あり、そのうち高齢者向け給付が約83兆円=60.1%にのぼっています 3 。 現役世代が増税でもなく補助金でもなく、「保険料」として自動的に支えている構造が、制度の不透明感や不信感の温床となっているのです。
この支出を支えているのは、私たち現役世代が負担する社会保険料です。 給与明細に含まれる健康保険、厚生年金、介護保険などの保険料負担は、年々じわじわと増え続けています。
たとえば、年収400万円の会社員(40歳以上)が負担する社会保険料は、年間で約64万円前後にのぼります。 これは年収の16%程度にあたり、さらに所得税や住民税を含めれば、手取りは全体の77〜78%程度にまで圧縮されます。
このように、現役世代は「暮らしのゆとり」を奪われながら制度を支えているにもかかわらず、自らが高齢者になったときには「同じ恩恵は受けられないのでは」という不安を抱えています。
年齢だけで一律支給される制度の限界
現在の高齢者福祉制度は、多くの給付や補助が「65歳以上」という年齢基準のみで設計されています。 かつては、高齢者=生活弱者という前提が成立していましたが、今やその現実は大きく変わっています。
高齢者のなかにも「持てる者」「働く者」の分断がある
総務省の家計調査によれば、高齢夫婦世帯(無職)の平均貯蓄は約2,400万円にのぼります4。 しかし、これはあくまで平均値であり、中央値は1,500万円以下。つまり、一部の資産リッチ層が統計を引き上げている構造です。
さらに注目すべきは、高齢者の中に存在する次のような逆転現象です:
- Aさん(資産はあるが無職) → 年金以外に収入なし。所得基準では「低所得者」とみなされ、各種補助の対象に。
- Bさん(資産はないので働いている) → 月数万円のパート収入あり。所得基準で「現役扱い」とされ、補助は減額または対象外。

このように、「持たざる者」が制度の外に追いやられ、「持てる者」が補助を受け続けるという逆転の構図が生まれているのです。
年齢=自動的に支援対象という仕組みの不公平
医療・介護・交通・住宅などの補助制度の多くが、いまだに「年齢」によって線引きされています。 結果として、資産を潤沢に持つ高齢者が自己負担1割で医療を受ける一方、働かざるを得ない高齢者や若年層は、割高な保険料や3割負担に直面しています。
これは、制度が実態から目を背けている証拠ではないでしょうか?
公平で納得できる制度へ
私たちは「年齢で一律に支援する」という仕組みから、「支援の必要性に応じて設計する」制度へと転換すべきだと考えます。 それによって、本当に困っている人に手を差し伸べ、将来世代の納得と持続可能性を取り戻すことができます。
現役世代にのしかかる負担と、「静かな崩壊」の兆し
高齢者福祉を支えているのは、現役世代が納める社会保険料です。たとえば、年収400万円の会社員は毎年約64万円もの社会保険料を負担しており、手取りは年収の77〜78%にまで圧縮されます。しかもその負担は「将来の自分のため」ではなく、現在の高齢者のために使われています。現役世代は、結婚や子育て、住宅取得といった人生の選択肢を削られながら制度を支えているにもかかわらず、自らが高齢者になる頃には、制度そのものが持たないのではという不安を抱いています。
この構造が続けば、制度は「誰も得をしない」ものへと崩れていきます。若者や子育て世代の信頼は失われ、票を持つ層へのバラマキが優先されることで、制度はポピュリズムの道をたどります。支える人が減り、守られるべき人も満足できず、社会全体に不満とあきらめが広がっていく――まさに「静かな崩壊」です。制度を支えるためには、「支える人が納得できる構造」であることが欠かせません。だからこそ今、痛みを分かち合いながら再設計することが必要なのです。
労働党の方針:削減ではなく、再配分と再設計を
1. 削減ではなく、「納得の再配分」へ
労働党が提案するのは、単なる「高齢者福祉の削減」ではありません。 制度の持続可能性を保ちながら、すべての世代が納得できる再配分の仕組みをつくること――それが、私たちの基本方針です。
高齢者の中にはすでに豊かな資産を持ち、支援を必要としない人も多くいます。一方、次世代を担う子どもや若年層、そして現役世代の多くは、将来への不安や生活の重圧に苦しんでいます。
限られた財源を、「支援が必要な人」に、「必要なとき」に届ける。 その公平な仕組みこそが、社会全体の信頼を取り戻す第一歩だと考えています。
2. 補助の半減と、その再投資の配分
私たちは、高齢者補助を段階的に半減し、浮いた財源のうち:
1/4を、子ども・若者への未来投資に (教育・保育・若年家庭支援・貧困対策など)
1/4を、現役世代の社会保険料の軽減に (給与明細に直結する「可処分所得の回復」)
と明示的に振り向けます。
この配分は、「誰のために、何に使うのか」をはっきりさせることにより、単なる負担軽減ではなく、社会全体の構造的な更新を目指すものです。
3. 支えられるだけでない、支える高齢期へ
そしてもう一つ大切なのは、 高齢者自身の「役割の再設計」 です。 支援を必要とする高齢者には確実に手を差し伸べつつ、支える力のある人には「もう一度、社会の一員として支える側に回ってもらう」ことを、制度として後押しします。
これは、単に負担を押し付ける話ではありません。 仕事、地域、ケア、教育などの分野において、高齢者が「必要とされる場」を用意し、社会との接続を保つことで、誇りある老後、健康で能動的な高齢期を支えるのです。
その具体策として、私たちは後のセクションで、「応能負担の導入」や「ベーシック・オキュペーション」などの制度を提案しています。
実現のための政策パッケージ
高齢者補助を一律に削ることは、現実的でも、公平でもありません。 私たちが提案するのは、必要な人には確実に支援を届けながら、そうでない部分を整理し直すという方向性です。 そのために、複数の政策を組み合わせた「政策パッケージ」として、制度全体の見直しを進めます。
まず、支出面では、医療・介護などの補助を応能負担化することで、支援が本当に必要な人に集中できるようにします。 同時に、所得だけでなく資産の状況も考慮した高齢者向けの資産課税を導入し、「持てる人」からの公平な負担を実現します。 一方で、「持たざる高齢者」や、生活のために働かざるを得ない人々には、補助の削減が逆に痛手とならないよう、手厚い支援を維持します。
また、役割と誇りを持てる高齢期を支えるために、年齢を問わず社会に参加できる仕事機会を整備する「ベーシック・オキュペーション」政策を拡充。 医療や介護、教育、地域づくりなどの分野で、高齢者が「必要とされる担い手」として活躍できる場をつくります。 さらに、高齢者の医療・生活インフラを集約した 「鉄道拠点都市」への移住支援制度 を通じて、分散型高齢化によるコスト増も抑制していきます。
これらの施策は、単独ではなく、 相互に補完し合う「構造改革のセット」 です。 支援の対象を見直し、負担のあり方を見直し、役割と居場所を再設計する。 労働党は、これらを一体で進めることによって、単なる「削減」ではない、持続可能で納得できる高齢者福祉のかたちを提案します。
実現のための政策パッケージ(個別政策一覧)
| 政策名(リンク) | 概要 | 予算インパクト |
|---|---|---|
| 高齢者医療の応能負担強化 | 医療費自己負担を、所得・資産に応じて見直し。必要な人への支援は維持。 | ▲8,000億円程度(高所得者補助の抑制) |
| 高齢者向け資産課税制度 | 資産規模に応じた応能負担を導入。低所得・高資産層への逆転支援を是正。 | +1.5兆円(再分配可能財源の創出) |
| 福祉給付の対象限定化 | 年齢一律支給を廃止し、資産・所得審査を導入。制度の的確性を向上。 | ▲5,000億円程度(非必要層への給付見直し) |
| ベーシック・オキュペーションの拡充(高齢者も含む) | 希望する高齢者に、地域・ケア・教育分野の社会的仕事を提供。 | ▲数千億円(給付から労働への転換による補助削減) |
| 鉄道拠点都市への移住支援制度 | 医療・交通インフラが整う都市への高齢者移住を促進。インフラ集約へ。 | ▲2,000億円程度(地域インフラコストの効率化) |
※ここに記載した削減額や再分配額は、正直に言って、まだ「補助を半減する」という目標には届いていません。 それでも私たちは、まず「何をどう減らし、何にどう振り向けるか」の方向性を明確に示すことが、政治における誠実さだと考えています。
すぐにすべてを実現できるわけではありません。だからこそ、政策の一つひとつを段階的に積み上げながら、“納得される制度”に近づけていくことを諦めない。 このパッケージは、その第一歩です。
ブログで背景を読む
👉 ブログ記事(外部) 「福祉給付の対象限定化の現実的な落とし所」
-
令和6年版高齢社会白書 第1章第1節1高齢化の現状と将来像より。図1-1-2参照 ↩︎
-
令和6年度予算政府案 より、社会保障関係予算 / 概要より。 ↩︎
-
令和6年版高齢社会白書 第1章第1節6 高齢化の社会保障給付費に対する影響より ↩︎
-
家計調査報告(貯蓄・負債編)-2024年(令和6年)平均結果-(二人以上の世帯) 要約 P.4 より ↩︎