経済改善 —— 成長でも脱成長でもない、もうひとつの選択肢
概要
これは、労働党が掲げる経済政策の中核です。 成長か縮小かの二者択一ではなく、社会の“底”から少しずつ豊かさを育て、 誰もが挑戦と安心を手にできる足場をつくる——それが、私たちのめざす「経済改善」です。
「経済改善」とは?
労働党が掲げる「経済改善」とは、いわゆる経済成長や脱成長といった従来の対立軸を超え、 社会全体の“底”から豊かさを育てることで、少しずつでも着実に暮らしを良くしていく経済政策です。
成長だけを追えば、成果は一部の成功者に集中しやすく、格差が広がります。 かといって、縮小を受け入れるだけでは、立ち直る機会を奪われた人々が取り残されていきます。
私たちは「誰もが再び立ち上がれる社会」を目指し、生活・労働・地域の基盤を耕し直すような経済の再設計を提案します。 成功を待つのではなく、不安や孤立から脱出できる道を増やすこと。 それが労働党の考える「経済改善」の出発点です。
経済成長とのちがい
従来の「経済成長」政策は、GDPの増加や企業収益の拡大を重視し、効率化やイノベーションによって“上へ伸びる”ことを目指します。 その成果は雇用創出や税収増を通じて国民に還元されるという「トリクルダウン」理論に立脚してきました。

しかし現実には、成長の果実は均等に行き渡らず、中間層の停滞や働く人の不安定化が進みました。 労働党は、「成長そのもの」を否定はしませんが、成果の偏在と格差の放置を前提にした政策では未来を託せないと考えます。
脱成長とのちがい
一方、「脱成長」は環境や持続性への配慮から、成長を前提としない生き方や縮小均衡の社会を志向します。 「足るを知る」「小さくて幸福な暮らし」といった価値観は、確かに一つの理想です。

ただし、すでに困難を抱えている人々にとって、現状維持は“停滞の固定化”に他なりません。 労働党は、「今ある不安を減らす」ことを重視し、救済や底上げの手立てを同時に講じる必要があると考えます。
底上げで、パイを増やす
経済改善は、格差是正や生活支援にとどまる「分配政策」ではありません。 すべての人の足元から環境を整え、“挑戦と参加”が当たり前の社会をつくることによって、結果として経済全体のパイを広げていく戦略です。

個人が再起できる社会、地域でお金と仕事が循環する仕組み、働くことが正当に報われる制度。 こうした基盤が整えば、人々は安心して生活し、次の一歩を踏み出せるようになります。 その積み重ねこそが、社会全体の活力と持続的な豊かさにつながるのです。
なぜ、経済改善なのか?──3つの理由
経済改善は「弱者支援」ではありません。 それは、 いまの日本社会を立て直すうえで不可欠な“前提の更新” です。 労働党がこの路線を選んだ理由には、次の3つがあります。
(1)成長の方向性は、民間が決めるべきである
「経済を成長させる」と言っても、どの分野が伸びるか、どの技術が花開くかは誰にも分かりません。 国や政党が「成長戦略」を掲げても、それが的中するとは限らない。むしろ、それぞれの現場や企業、ベンチャーが自由に挑戦し、試行錯誤の中で未来を切り開くべきです。
だからこそ政治の役割は、トップダウンで「何を育てるか」を決めることではなく、土壌を耕し、芽が出やすい環境を整えることにあると考えます。
(2)挑戦を支える仕組みが、あまりにも脆い
たとえ意欲があっても、日本社会では 挑戦することそのものが「リスク」 になってしまっています。
- 離職すれば収入が絶たれる
- 生活保護は受けにくく、制度は画一的
- 結婚や子育てといった個人の選択すら、「損」と感じさせてしまう社会
こうした状態では、人は身動きが取れません。 挑戦できない社会は、成長しない社会です。
本来、政治は「何に挑戦すべきか」を決めるのではなく、挑戦を妨げない仕組みとセーフティネットを整えることで、すべての人の可能性を後押しすべきです。
(3)底上げこそが、もっとも確実な経済政策である
近年の経済政策は、「選ばれた産業」「トップ層」に支援や富を集中させる傾向が強まりました。 しかし、成果の集中は必ずしも分配につながらず、むしろ格差や孤立を広げる結果になってきました。
労働党は、こう考えます。
「すでに足りている場所に投資しても、限界がある。 足りていない場所を底上げしたほうが、社会全体のパイは大きくなる。」
生活の安心、労働の報酬、地域経済の循環── それぞれの“足元”を豊かにすることこそ、最も持続的で、実効性のある経済政策なのです。
経済改善が向き合う3つのターゲット層
経済改善は「国民すべてを対象とした政策」ですが、なかでも構造的に支援が不足している3つの層に重点を置いて設計されています。 それは、社会を支えてきたのに報われず、また未来への準備すら整えられていない人々です。
① 中間層 ——「支えすぎて疲れた人たち」
長年、税と保険料で社会を支えてきた世代。 しかし、生活には余裕がなく、将来への信頼も薄れています。
- 高すぎる社会保険料、複雑で不透明な制度
- 子育てや住宅ローンを諦める「消極的選択」
- 現在も将来も「見通しが立たない」不安
経済改善では: 社会保険料の適正化や制度の透明化で、中間層に「希望の再分配」を行います。
② 低所得職種の労働者 ——「不可欠なのに報われない仕事」
介護・保育・飲食・物流・清掃…… 私たちの生活を支える仕事は、なぜこんなにも不安定なのか。
- 時給は最低限、キャリアも給与も伸びづらい
- 社会的価値が高いのに、経済的評価が低い
- 離職率の高さが、労働環境の悪化を加速させる
経済改善では: 最低賃金の底上げや報酬評価の導入により、「働くほどに安定する」社会の再構築を図ります。
③ 社会的困難者(就労困難層)——「やり直す場所がない人たち」
病気、障害、育児、介護、ひとり親、孤立、住居喪失…… どれも「特別な事情」ではなく、誰にでも起こり得る現実です。
- 「働けない=支援を受けられない」構造
- 生活保護のハードルが高く、再出発が難しい
- 自助・共助が前提の仕組みに置いていかれる
経済改善では: 生活・就労・住居の包括支援によって、「もう一度やり直せる社会」をつくります。
この3層は「別の誰か」ではありません
これらの層に「属している」と気づいていない人も多くいます。 しかし、病気、リストラ、育児、介護──誰もが一時的にこの層に属する可能性があるのが現実です。
労働党の経済政策は、こうした「今は声を上げられない人」こそ、確実に支えられる社会を目指します。
「経済改善」の方法論
全体概要:5つの柱で、社会の足元を耕し直す
経済改善は、「ひとつの政策」ではなく、仕組みそのものを根本から組み直す複合的な取り組みです。 労働党はこれを、以下の5つの柱によって実現していきます:
| 支える対象 | 必要な支援の方向 | 経済改善の柱 |
|---|---|---|
| 中間層 | 負担の是正 | ① 社会保障の持続可能化 |
| 低所得職種 | 評価の再構築 | ② 働くことの再評価 |
| 社会的困難者 | 自立の再構築 | ③ 自立再建と社会参加 |
| 地域経済 | 循環の再生 | ④ 地域経済の循環強化 |
| 全体財源構造 | 再分配と公平性 | ⑤ 公正な財政と資本課税 |
これらは、個人・地域・国家の3つのレベルで機能する設計です。
- 個人にとっては: 不安や孤立を減らし、「次の一歩」を踏み出せる足場を整える
- 地域にとっては: 雇用と消費の地産地消を促進し、持続的な経済循環を生み出す
- 国家にとっては: 安定的な再分配と公平な課税を通じて、将来への投資財源を確保する
このように、単なる一時的な対症療法ではなく、“土台そのもの”を強くし直す政策群こそが経済改善です。
社会保障の持続可能化 —— 支える人が、支えられる社会へ
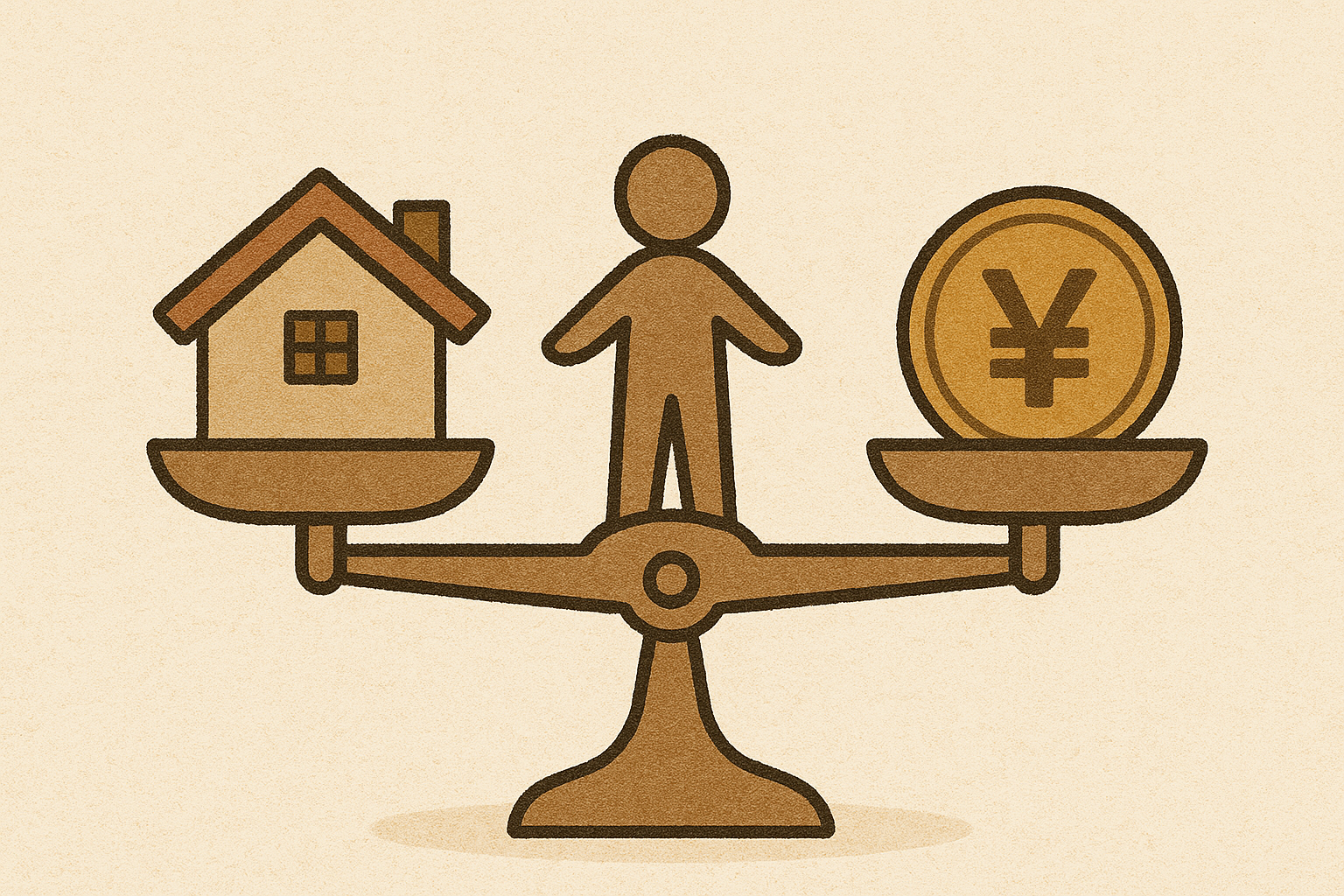
いま、日本の社会保障制度は「支える人」が疲弊する構造になっています。 年金・医療・介護・子育て支援の多くは中間層の保険料で賄われていますが、彼ら自身の生活は余裕を失いつつあります。 このままでは「納める人」と「受け取る人」の分断が深まり、制度全体の信頼が揺らぎかねません。
とくに近年は、高齢者の間にも格差が生じていることが、制度不信を加速させています。 資産を十分に保有し、引退後も安定して暮らせる高齢富裕層と、年金や医療費が暮らしを圧迫する高齢貧困層。 この“世代内格差”に目を向けることなく、ただ「高齢者全体を支える」構造を続けることは、現役世代にとって大きな不公平感の源となっています。
労働党は、高齢世代の内部にある格差にも向き合い、富裕層から貧困層へと再分配を促す設計を導入します。 これにより、世代内の公平性を高め、結果として世代間の対立構造そのものを和らげることを目指します。
私たちは、社会保障制度を「誰もが支え、誰もが支えられる」仕組みへと再設計します。
主な取り組み
- 社会保険料の適正化(応能負担の強化) 高所得者や高資産者の負担能力に応じた保険料・自己負担を設定し、中間層の負担を軽減
- 制度の透明化・簡素化 「なぜこれだけ徴収されるのか」「どう使われているのか」を明確にし、納得して支えられる制度に
- 世代間・世代内の公平性確保 高齢富裕層への過度な給付を見直し、「世代を超えた負担と恩恵のバランス」を再調整 ※必要に応じて、高齢世代の資産保有状況に応じた 負担の見直し(資産課税を含む) も検討
- 保険外サービスとの連携強化 自治体・企業・地域団体による補完的な支援を制度内に位置づけ、共助と公助の橋渡しを促進
対象となる人々
- 「支えてきたのに、将来が見えない」中間層の現役世代
- 高すぎる負担に生活設計が立たない子育て世帯
- 制度の複雑さ・不透明さに不信感を抱く納税者全般
Before → After
| 現状 | 改善後 |
|---|---|
| 毎月の社会保険料が重すぎて、生活費を圧迫 | 負担が適正化され、生活設計に余裕ができる |
| 制度が複雑で不透明。「何に使われているのか分からない」 | 仕組みが分かりやすく、説明も丁寧。納得感がある |
| 「支える側ばかり損をしている」という不公平感 | 「誰もが支え、誰もが支えられる」バランスのとれた制度へ |
この柱は、中間層の信頼とゆとりを取り戻すことを目的としています。 制度を支える現役世代こそが、未来の希望を育てる存在である── その前提を回復することから、経済改善は始まります。
働くことの再評価 —— 不可欠な仕事が、報われる社会へ

いまの日本では、社会に不可欠な仕事ほど低賃金で不安定です。 介護、保育、清掃、物流、飲食など、日々の暮らしを下支えする職種の多くが、「やりがい」だけで成り立つ構造に放置されています。
こうした仕事は、単に「雇用の場」や「サービス提供」ではありません。 それは、私たちが毎日を生きるうえで欠かせない、社会そのものを維持するための機能です。
しかし現在の制度や市場は、「利益を生むかどうか」だけを価値基準として評価してしまいがちです。 その結果、本来もっとも重要なはずの仕事が、社会の中で軽視され、十分な報酬も保障されていません。
労働党はここに、原則的な問いを投げかけます:
「社会」がなければ、「市場」も存在できない。 だからこそ、社会を支える仕事には価値を見出すべきだ。
この視点に立ち、「不可欠な仕事が、報われる社会」を実現します。
主な取り組み
- 最低賃金の大幅な底上げ 地域格差の是正も含め、全国一律の最低賃金引き上げを段階的に実施
- スキル・責任に応じた報酬評価制度の整備 とくにケア労働(保育・介護など)に対して、公的な加点評価や手当支給の仕組みを導入
- 公共調達における報酬基準の明示化 政府・自治体が発注する業務(委託・外注)において、低価格競争による賃金圧縮を防ぐ
- 現場主導の業務改善・負担軽減支援 過重労働や離職リスクの高い現場に対して、職種別に予算と人員の「再設計支援」を行う
対象となる人々
- 最低賃金ぎりぎりで働く非正規・パート・フリーランス
- 保育・介護・福祉・清掃・飲食などのサービス職従事者
- 賃金が労働負荷や責任に見合っていないと感じている人
Before → After
| 現状 | 改善後 |
|---|---|
| 「必要だけど、儲からない」職種が多すぎる | 社会的に必要な仕事ほど、安定した報酬が得られる |
| スキルや責任が正当に評価されていない | スキル・負荷に応じた報酬制度が整っている |
| 公共事業でも価格優先で賃金が削られる | 国や自治体が「安かろう悪かろう」発注を是正 |
この柱は、社会の持続性を根底から支えるための「価値の見直し」です。 働くことは単なる生計手段ではなく、社会とのつながりであり、誇りの源です。 その「誇り」がきちんと報われるように制度を整えることは、誰かのためだけでなく、社会全体の健全な土台をつくる行為だと、私たちは信じています。
自立再建と社会参加 —— やり直しがきく社会へ

「働けない」ことは、怠けや甘えではありません。 病気や障害、介護、育児、ひとり親、スキル不足、地域的孤立—— どれも、誰にでも起こりうる現実です。そしてそれは、人生の一時的な段差にすぎないことも多い。
にもかかわらず、日本社会は一度つまずいた人を労働市場から“除外された存在”として扱いがちです。 生活保護のハードルは高く、支援制度は複雑で、誰にも相談できないまま孤立する── そうした人々に対して、私たちは「もう一度、働いてもらう」ための支援を本気で行います。
労働党の経済改善は、単なる生活補助ではありません。
目指すのは「自立」ではなく、「再建」—— もう一度這い上がり、働き、社会とつながってもらうこと。 そのための制度と環境を、全力で整えることです。
しかもそれは、本人の人生にとってだけではなく、社会全体にとっても極めて合理的な投資です。
「働けない」と諦めていた人が「働ける!」ともう一度立ち上がれば、
- 社会参加によって自尊心と居場所が回復し、
- 新たな労働力として経済活動を支え、
- 福祉給付の継続的負担も減らすことができる。
“排除される存在”ではなく、“もう一度担う存在”として受け入れる。 それこそが、持続可能な社会への本質的なアプローチだと、私たちは考えます。
主な取り組み
- 住まい・生活・就労支援の一体提供 「働く」以前に必要な住居や生活基盤を確保し、困窮の連鎖を断つ
- ベーシック・オキュペーション(最低限の仕事保障) 公共・ケア・教育・環境などの分野で、**誰もが担える“社会的に必要な仕事”**を創出し提供
- 地域での参加・役割の創出 就労に限らず、地域活動や福祉的就労など多様な“参加の場”を用意し、社会的孤立の解消へ
- 段階的なステップアップ制度 スキルや体力に応じて、無理のない形で「自立」へ向かう仕組みを整備(例:就労訓練+賃金保障)
対象となる人々
- 病気や障害、育児、介護などで働けない状況にある人
- 長期離職や住居喪失により社会と接点を失った人
- 「いまさら再就職は難しい」と感じている中高年層
- 就労意欲はあるが、スキル・経験・居場所が足りない人
Before → After
| 現状 | 改善後 |
|---|---|
| 「働けない=支援が受けられない」 | 「働けない時も、次を準備できる」制度がある |
| 生活支援・就労支援がバラバラでつながらない | 住まい・暮らし・仕事を一体で支援 |
| 社会とのつながりが絶たれ、孤立する | 地域や公共の中で再び役割を持てる |
この柱が目指すのは、 「自立」ではなく「再建」 です。 一度つまずいた人が、もう一度やり直せること。 それは本人のためだけでなく、社会の持続性そのものを支える投資でもあると、労働党は考えます。
地域経済の循環強化 —— 地元に仕事とお金が残る仕組みへ

地域の多くは今、地元にお金も仕事も残らず、若者が都市へ流出し続ける悪循環に陥っています。 医療・介護・保育・交通といったインフラも限界に近づき、地域で暮らし続けること自体が不安になってきている—— そんな声が各地で聞かれるようになりました。
労働党は、こうした状況を変えるために、「人が地域に残れる理由」をもう一度つくりなおすことを目指します。 介護・保育・教育・交通など、生活を支える仕事を地元で雇用として成立させ、 そのお金が地域内で回る仕組みを支援します。
そして同時に、すべての地域が分散して存続するのではなく、 拠点を絞り、暮らしやすさを集約する“コンパクトシティ”の形成を各地で進めます。
若者は地元で働き、子育て世代は便利で効率的に暮らせる。 高齢者は移動や医療に困らず、安心して地域にとどまれる。 そうした「未来に希望が持てる地域」をつくることが、 地域経済の循環と、社会インフラの持続可能性を両立させる鍵になると、私たちは考えています。
主な取り組み
- 地域サービス雇用の創出 介護、保育、教育、環境、交通など「地域に必要な仕事」を地域内で雇用として成立させる仕組みを整備
- 協同組合・社会的企業の支援 営利だけを目的としない「地域主導の経済主体」への資金援助・税制優遇・人材育成支援を実施
- 自治体による“地域調達”の推進 自治体が外部大手に丸投げするのではなく、地元業者・団体からの発注を優先する公共契約モデルを確立
- 地域通貨・地域ポイント制度の実験支援 お金の循環を地域内にとどめる新たな仕組みを、地方自治体や商店街と連携して試行
対象となる地域・人々
- サービスや雇用が外部依存になりがちな地方自治体
- 地元の中小企業や福祉事業者、商店街、NPOなど
- Uターン・Iターンを検討する移住希望者や若年層
- 公共インフラや生活支援の担い手が不足している地域
Before → After
| 現状 | 改善後 |
|---|---|
| 地元の税金で、外部企業に発注 → 地元に雇用が生まれない | 公共事業が地域内雇用・地元循環を促す |
| 介護や保育、交通などが担い手不足で崩壊寸前 | 「必要な仕事」に地域の人が関われる仕組みを再設計 |
| 若者が地元に戻れず、都市への流出が止まらない | 地元にも働く場と役割があり、暮らしの選択肢が増える |
この柱が目指すのは、「地方を救う」ことではなく、「地方とともにつくる」ことです。 一極集中ではなく、多極分散型の社会へ。 その実現には、経済の流れそのものを地域に根づかせる発想が不可欠です。
公正な財政と資本課税 —— 持てる者が、少し多めに支える社会へ

社会には、誰かが支え手にならなければ成り立たない部分があります。 いま日本の財政は、消費税や社会保険料といった“みんなで薄く広く負担する”仕組みに過度に依存し、 現役世代や中間層にしわ寄せが集中しています。
その一方で、十分な資産を持つ人々、収益を上げ続ける大企業が、 制度の隙間や既得の枠組みに守られ、相対的に軽い負担で済んでいるのもまた現実です。
私たちは、この不均衡を放置することはできません。 次の世代へ持続可能な社会をつなぐために、 「持てる者が、少し多めに支える」構造へと切り替える必要があると考えます。
そしてそのことは、感謝と敬意なしには語れないとも、私たちは思っています。
たくさん持っている人へ。 社会のために、あとほんの少し、お願いできないでしょうか。 いま、この国を維持するために、どうしても必要なんです。
……ごめんなさい。でも、ありがとうございます。
労働党は、こうした正直で誠実な説明を尽くしたうえで、 応分の負担と納得の再構築を進めていきます。
主な取り組み
- 資産課税の強化と累進性の見直し 富裕層への相続税・贈与税・キャピタルゲイン課税を再設計し、保有資産に応じた応能負担を徹底
- タックスヘイブン対策と大企業優遇の是正 国際課税の枠組みに参加し、海外移転やグループ内取引による“節税”を制限。中小企業との税負担格差を縮小
- 財政支出の選別と効果検証 不要不急の大型公共事業や政治的バラマキを抑制し、費用対効果に基づいた支出改革を推進
- 「財源なき理想論」からの脱却 すべての政策に財源根拠を明示し、説明と合意を重視する税・予算運営へ転換
対象となる税・制度
- 相続税・贈与税・所得税の高所得層部分
- 株式・資産売却益(キャピタルゲイン課税)
- 国際法人税・BEPS対応
- 政府支出の見直し(透明性の確保)
Before → After
| 現状 | 改善後 |
|---|---|
| 消費税や保険料が「中間層以下」に重くのしかかる | 「持てる人・法人」が少し多めに支える構造へ |
| 富裕層や大企業が“抜け道”で課税を回避 | 海外含めた資本にも公平な課税が届く仕組みへ |
| 政策は夢物語、財源はブラックボックス | 政策ごとに明確な財源設計と説明責任がセットに |
この柱は、単なる“課税強化”ではありません。 「誰もが支える社会」から、「支えられる人が、少しだけ多めに支える社会」へ。 それは、未来に向けた連帯であり、投資であり、信頼の基盤なのです。
どこへ行くのか?──未来像の提示
経済改善という政策は、「足元を耕し直す」ような取り組みです。 日々の生活の不安を減らし、誰もが挑戦できる足場を整え、地域の経済に再び息を吹き込む── それは一つ一つは地味で、小さな変化に見えるかもしれません。
けれど、そうした小さな積み重ねこそが、社会全体をじわじわと変えていきます。
私たちが目指すのは、そうしてたどり着く、ひとつの未来です。 その姿を、私たちは「黄金の2050年」と呼んでいます。
2050年、日本の朝。 人々は目覚めて、自分の暮らしを少し誇らしく感じられる。 「今日もなんとかなる」「明日はもっとよくなるかもしれない」── そんな実感を、ごく当たり前のものとして抱いていられる社会。
たとえば、子どもを育てるという選択が、重たい決断ではなく、希望に満ちた自然な行為になる。 たとえば、仕事に失敗したり、病気になったりしても、「次がある」と思える。 たとえば、自分には何の特別な能力もないと思っていた人が、地域の中で必要とされていると感じる。
そうした小さな幸福が、積み重なって広がっていく未来です。
「黄金」とは、ぜいたくや富のことではありません。 それは、人々が自分の暮らしに意味を見出し、つながりの中で息をしているということです。
そのために必要なのは、成長か、縮小か、という単純な問いではありません。 社会全体の土壌を耕し直し、誰もが挑戦できて、誰もが安心できて、誰もが未来に希望をもてるようにすること。 労働党の経済改善は、その道筋をつける取り組みです。
この国に生きるすべての人に、「生きていてよかった」と思える明日を。 経済改善の名のもとに、私たちはそれを本気で目指します。
このような形で文章を構成しました。 詩的すぎる・論理をもう少し強めたいなど、調整ご希望あればお申しつけください。
関連政策へのリンク
本ページで紹介した「経済改善」の理念と5つの柱は、それぞれが具体的な個別政策として展開されていきます。 以下は、現時点で公開されている関連政策ページの一覧です。今後も議論と検討を重ねながら、随時追加・更新されていきます。
公正な財政・税制に関する政策
社会保障・負担構造に関する政策
働くことの再評価に関する政策
再挑戦・自立支援に関する政策
地域経済と雇用に関する政策
上記以外にも、教育、子育て、デジタルインフラ、地方自治、住宅政策など、経済改善と密接に関わる分野の政策群が順次整備されています。 すべての政策は、 「誰かのため」ではなく「私たちのため」 という視点から、公開・説明・議論可能なかたちで展開されていきます。